まえに、いるひと MAE PEOPLE

まえに、いるひと MAE PEOPLE
地域を想い、世界に羽ばたく——能作とMAEが描く、グローカルの可能性
能作千春(株式会社能作 代表取締役社長) Katsuji Nousaku, Chiharu Nousaku

-
富山は、山も海も近く、自然の恵みにあふれた土地。そんな場所で生まれた企業たちは、地域の伝統や文化を大切にしながら、新しいことにもどんどん挑戦している。今回話を聞いたのは、100年以上にわたって鋳物を作り続けてきた「能作」と、60年以上製薬に取り組んできた「MAE」。ものづくりの分野は違っても、共通するのは「世界を見据えた挑戦」と「社員の成長を大切にする姿勢」、そして「地域とのつながり」だ。
下請け中心だった能作は、いまや自社製品が9割となり、年間13万人が訪れる産業観光のスポットにもなっている。一方のMAEは、製薬の枠を超えてアロマやジン作り、さらにはホテルやサウナまで手がけるなど、次々と新しい挑戦を仕掛けている。
伝統を守りながらも、挑戦を恐れない。地域に根ざしながら、世界を見据える——そんな両社の発想の源泉を探るべく、能作代表取締役会長・克治さん、社長・千春さん、そしてMAEの石川に話を聞いた。



-
富山から新しい価値が生まれる瞬間
富山の高岡市で注目を集める鋳物メーカー「能作」。しなやかに曲がる「KAGO」シリーズなど、斬新なアイデアの製品が世間を驚かせている。そして本社工場は、ただ製品を作るだけの場所にとどまらず、年間13万人以上が訪れる観光スポットにもなっている。
能作が工場見学を始めたのは、約40年前のこと。代表取締役会長の能作克治さんは、そのきっかけをこう振り返る。
「ちょうど千春(現社長)が生まれる少し前のことです。当時、うちは分業体制の中で『生地屋』と呼ばれ、問屋さんから仕事をもらって、彫金や着色を施す前の状態の鋳物をつくる工程を担当していました。工場見学を始めたのも、その頃からなんです。」
1980年代後半、日本はバブル景気真っ只中。ホワイトカラーの仕事がもてはやされる一方で、ものづくりの現場は軽視されがちだった。そんな時代に、克治さんの心に深く刻まれる出来事が起こる。
「ある日、地元の女性から電話があったんです。『息子に伝統産業の勉強をさせたいから、工場を見せてもらえませんか?』って。それで当日、一生懸命鋳物づくりの現場を見せたんですが、そのお母さんが息子に言ったんです。『あんた、よく見なさい。勉強せんかったら、こんな仕事やからね』って。」
それを聞いて、思わず言葉を失った克治さん。伝統産業の街・高岡では、かつて人口の半分近くが鋳物産業に携わっていたはず。それなのに、地元の人たちですら、その価値を正しく理解していないことに気づいたからだ。
「これは高岡だけじゃなくて、日本中の伝統産業が抱えている問題なんですよ。『おじいちゃんおばあちゃんがやっている仕事』みたいなイメージを持たれてしまっている。でも、この意識を変えたい。まずは地元から変えていこうと思って、工場見学を本格的に始めたんです。」
これが少しずつ広がり、やがて年間1万人以上が訪れるまでに成長。2017年には、豊かな自然に囲まれた約4,100坪の土地に新たな本社工場を建設。見学や体験工房、カフェを併設した素敵な空間に生まれ変わった。
そして今、能作が見据えるのは全国だ。
「最初は、高岡や富山の人に伝統産業の魅力を知ってもらいたいと思っていました。でも、今では全国からたくさんの方が足を運んでくださるようになり、日本の伝統産業そのものを変えていきたいという思いに変わってきたんです。ただ、どんな時も心がけているのは“独り占めしない”こと。みんなでシェアしながら、伝統を未来につないでいく。それが能作のやり方です。」
能作が産業観光を通じて地域の魅力を発信している一方、また違ったアプローチで富山のポテンシャルを引き出している企業がある。それが、MAEだ。
製薬だけにとどまらず、アロマ事業や複合施設「ヘルジアンウッド」の運営、さらには「新蒸留研究所」でジンの製造にも挑戦するなど、富山の自然や文化を生かした取り組みを次々に仕掛けている。
そのプロジェクトをリードするのは、長年製薬業界で薬剤師としてキャリアを積んできた石川和則。医薬品一筋だった彼が、富山に移住して新たな事業を模索している中でたどり着いたのは、地域の魅力を伝える、ちょっと意外な視点だった。
「富山には本当に素晴らしい資源や技術がたくさんあります。でも、僕たちが大事にしているのは、単に『富山産』っていうラベルを押し出すことじゃないんです。」
能作が産業観光を通じて地域の魅力を発信している一方、また違ったアプローチで富山のポテンシャルを引き出している企業がある。それが、MAEだ。
製薬だけにとどまらず、アロマ事業や複合施設「ヘルジアンウッド」の運営、さらには「新蒸留研究所」でジンの製造にも挑戦するなど、富山の自然や文化を生かした取り組みを次々に仕掛けている。
そのプロジェクトをリードするのは、長年製薬業界で薬剤師としてキャリアを積んできた石川和則さん。医薬品一筋だった彼が、富山に移住して新たな事業を模索している中でたどり着いたのは、地域の魅力を伝える、ちょっと意外な視点だった。
「富山には本当に素晴らしい資源や技術がたくさんあります。でも、僕たちが大事にしているのは、単に『富山産』っていうラベルを押し出すことじゃないんです。」
そう話す石川が大切にしているのは、製品そのものの価値。
「大事なのは、製品が持っている品質やストーリーです。地域の名前を前面に出すよりも、丁寧なものづくりと高い品質を追求する。それが、結果的に富山の魅力を自然に伝えることにつながると思っています。」
この考え方は、能作の理念にも通じるところがある。地域性を売りにするのではなく、ものづくりの本質的な価値を追求する。そんな姿勢が、地域の魅力を伝えていくことに繋がるのだ。
能作が産業観光を通じて鋳物の価値を再発見したように、MAEもまた、新蒸留研究所などのプロジェクトを通じて製薬業界における新たな観光資源の可能性を探っている。富山の素材や伝統を生かしながらも、ただ「富山のもの」と言うのではなく、もっと本質的な価値を掘り下げていく。それが、地域を超えて多くの人々を惹きつけている理由なのかもしれない。

-
進化するからこそ、伝統になる
千春さんが能作に入社してから、数々の新しい取り組みが始まった。たとえば、2019年にスタートした「錫婚式」は、同社が扱う材料である錫に注目して立ち上げたブライダル事業。金婚式、銀婚式のように、結婚10周年は「錫婚式」と呼ばれることから、錫を用いたオリジナルの挙式や記念品作り、錫の食器を使った特別料理を楽しめるユニークな取り組みだ。
そして、2020年9月には地域の魅力を体験として届ける「想い旅」がスタートし、現在は「観光×宿泊プラン」へと進化している。いずれも、ただのビジネスではなく、「地域に根ざした価値あるものにしたい」という千春さんのこだわりが反映されたものだ。「伝統産業って、ただ守るだけじゃなく、新しい道を切り拓くことが大切なんです。」
千春さんにとって、伝統と革新はむしろ切っても切れない関係。伝統を未来につなげるためには、常に新しい挑戦が必要だと感じているからこそ、錫婚式や産業観光のような新しい事業が生まれたのだろう。
「錫の可能性を広げることも、錫婚式という新しい文化をつくることも、すべては伝統を次世代につなげるため。新しい事業を通じて生まれる資金や、社員の成長の機会も、伝統産業を持続させる上でとても大切だと考えています。」
事業が成長するにつれ、新たな課題も生まれた。製造業だけでなく、飲食やブライダルへと広がる中で、どうやって社員たちが一丸となって進んでいけるか。それが大きなテーマになった。
「社員が増えると、それぞれの役割も多様化します。だからこそ、共通の価値観を持つことが大事なんです。」
そこで能作では、2ヶ月に1回、社員全員が学べる場を設け、他社や地域の専門家を招いて視野を広げる機会をつくっている。さらに、社内向けの「能作図鑑」をつくり、部署ごとの仕事だけでなく、社員一人ひとりの志や価値観を共有することで、会社の軸がぶれないようにしている。
産業観光の取り組みも、社員たちの成長に大きく貢献した。初めは「話すことが苦手だし、観光客の対応ができるのか…」と戸惑う職人も多かった。しかし、実際にお客様と話すうちに、「作り手が直接伝えること」の大切さに気づくように。今では、職人が接客をするのも、スタッフが製造現場を訪れるのも当たり前に。自然と部門の垣根を超えたチームワークが生まれている。
能作の企業文化は、社員一人ひとりが自分ごととして関わることで、より強く、しなやかに成長し続けている。伝統を未来につなぐその姿勢は、ものづくりの可能性を広げる大きなヒントになりそうだ。




- 変化を楽しむから、未来が生まれる
-
MAEでは、今、いくつもの新しい挑戦が動き出している。そのひとつが「新蒸留研究所」。石川自身も、薬剤師から新規事業の立ち上げへとフィールドを広げる中で、これまでの医薬品事業の知見を活かしながら、社員が成長できる環境づくりに力を入れている。
「自分たちが手がける製品やサービスに誇りを持ち、外からの評価を直接感じられる機会をつくること。それが、一人ひとりのモチベーションにつながると思うんです。」
新蒸留研究所には、自ら手を挙げた社員たちが集まっている。社長である前田からの熱いメッセージも後押しとなり、それぞれが強い意志を持って取り組んでいる。
「MAEの新規事業に関わる社員は、みんなそれぞれの覚悟を持っています。だからこそ、社内で成功体験を積み重ねることが大切でした。一年間かけて新しい挑戦に興味を持つ仲間を探し、少しずつチームを作っていきました。」
この取り組みの根底にあるのが、「人と社会に新陳代謝を」というMAEのビジョンだ。
石川は、こう考える。
「生き物の本質って、新陳代謝にあると思うんです。ずっと同じ状態ではいられないし、変化し続けることで健全に成長できる。それは、人も社会も同じですよね。」
もしも10年前と同じ仕事を上の世代が続けていたら、若い世代が新しい価値を生み出すチャンスは生まれない。だからこそ、経験や知識を受け継ぐだけでなく、それを組み合わせて新しいものを生み出していくことが大事なのだ。
MAEでは、社員が持つ専門性を活かしながら、新しい分野にも挑戦できる環境づくりを進めている。
「医薬品の知識や科学的な思考、品質へのこだわりは、医療以外の分野でもきっと役に立つはず。そう考えると、可能性って無限に広がるんですですよね。」
石川自身も、新しい分野に挑戦することで、社員にとってのロールモデルになろうとしている。
「未知の世界に飛び込むと、必ずワクワクする発見があります。その経験が、自分を見つめ直すきっかけになり、次の目標が見えてくる。その循環を続けることで、個人も、組織も、どんどん成長していけると思うんです。」
そんなMAEの姿勢に刺激を受け、能作でも新たな取り組みが始まっているらしい。
「MAEさんの社内コンペの話を聞いて、私たちも挑戦してみることにしました。社員が主体的に動いてアイデアを出せる場を作るのは素晴らしいですよね(千春さん)」
一方で、MAEも能作から多くの学びを得ている。
「能作さんの挑戦する姿勢には、すごく刺激を受けています。新しいことを始めると、迷いや葛藤はつきものですが、能作さんと一緒に仕事をする中でいただいたアドバイスを思い出しながら、いつも原点に立ち返っています(石川)」
互いの挑戦が、新しい気づきを生み出し、社員の意識を変えていく。その積み重ねが、組織全体の新陳代謝を促している。変わり続けることこそ、企業が成長するための原動力なのかもしれない。

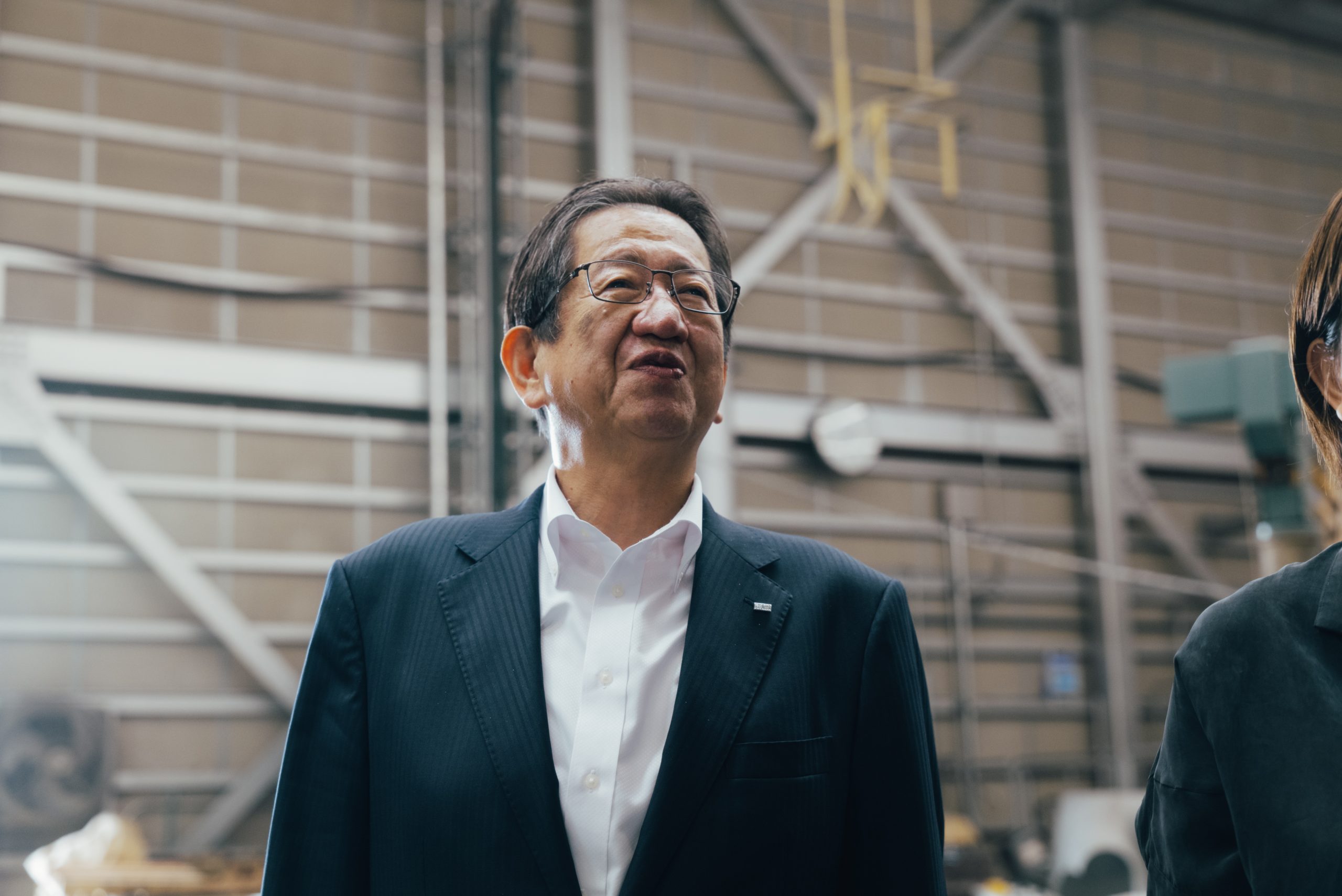
- 地域に根ざし、愛される企業とは?
-
企業と地域が共に成長し、支え合うこと。それこそが、本当に強いビジネスの形なのかもしれない。
「地域のために動くことが、本当に大切なんです。」
そう語るのは、克治さん。伝統産業を守りながら、地域の人々に愛され、巻き込んでいく。そんなビジネスのあり方こそが、長く続く企業の秘訣だという。
そして千春さんは、企業の本質を「究極的には、人を幸せにすること」と考えている。だからこそ、産業観光やイベントを通じて、地域の子どもたちや住民にものづくりの魅力を伝え、職人の誇りを育んできたのだ。
面白いことに、能作には営業担当がいない。しかし、驚くべきことに、地域の人々が自然と企業の魅力を広めてくれている。実際、タクシーの運転手が紹介してくれたことで観光客が訪れることも珍しくない。
「まずはここに来てもらうこと。そして、高岡という街に興味を持ってもらう。その結果、能作のファンになってもらうことができ、地域全体の活性化にもつながるんです。」
能作の本社施設にある「TOYAMA DOORS」というコーナーでは、富山の魅力的なスポットや産業を紹介している。これは能作単体の魅力を高めるだけでなく、地域全体の価値を引き上げる仕掛けにもなっている。このような取り組みが地域との信頼を深め、最終的に能作自身のブランド力を高めることにもつながっている。
また、能作は業界を超えたコラボレーションにも積極的だ。
「地元の水産業や農業従事者の方々と一緒に、富山の魅力を発信する機会をいただいています。異業種との連携で地域の価値を高められるのは、企業としても非常にありがたいことです。」
MAEが大切にしている「製品そのものが語るストーリー」と、能作が進める「地域全体の価値を高める産業観光」。アプローチは違えど、どちらも「富山の価値を広めたい」という思いは共通している。
「人生も同じです。どれだけ多くの人を幸せにできたかが、その人の価値だと思っています。」
克治さんの言葉には、企業の本質が詰まっている。利益を追うだけではなく、地域や社員、そしてお客様の幸せを大切にすること。それこそが、持続可能な成長につながっていくのだろう。
伝統と革新を融合させ、地域の価値を高め続けるMAEと能作。
単なるビジネスの枠を超え、地域とともに歩むその姿勢が、新たな可能性を切り拓いている。

-
富山の魅力を、世界へ
「富山の魅力って、なんだろう?」
そんな問いに、千春さんは迷わず答えた。
「人の温かさ、ですね。」
県外で暮らしたからこそ、富山に戻ってきたときに感じた、人とのつながりの深さ。何か新しいことを始めたいと思ったとき、必要な人と自然につながれる。そんな空気が、富山にはある。
「富山には、地域全体で新しい挑戦を応援する文化があるんです。」
克治さんも、「富山では、誰かが道を切り開くと、みんなが自然と後に続くんです」と語る。挑戦する人が現れると、それを支える人たちが集まり、やがて次のチャレンジャーが生まれていく——そんな循環が、富山の土地に根づいているのかもしれない。
そして、この地域ならではの自然環境も、クリエイティブな発想を後押ししてくれている。
「東京にいたら、たぶん思いつかなかったと思います。富山の水があるからこそ生まれたアイデアもあるし、ここで暮らすことで、目の前のことだけじゃなく、もっと長いスパンで物事を考えられるようになりました。」
そう話すのは、ジンの製造に携わる石川だ。
環境が変われば、ものの見方も変わる。富山だからこそ生まれるものづくりが、確かにある。


- 文化の違いがチャンスになる
-
地域に根ざしたものづくりを大切にしながら、世界へと挑戦する——MAEと能作が目指すのは、そんな未来だ。
「Think Global, Act Local(世界規模で考えて、地域で行動する)」
この言葉のとおり、能作は高岡の地でものづくりを続けながら、その価値を世界へ届けている。伝統を守りながら、時代に合わせた進化を重ねてきた。
海外に目を向けると、文化の違いが新たなヒントになることも多い。
「日本では、金属ってちょっと冷たい印象がありますよね。もしかすると、武器として伝わった歴史が影響しているのかもしれません。でも、大陸では金属文化が根付いていて、日本とはまったく感覚が違うんです。」
そう語るのは、克治さん。
たとえば、結婚記念日を祝う風習はヨーロッパから広まったとされ、イギリスには結婚10周年を祝う「錫婚式」という文化がある。でも、世の中には錫製品の選択肢がまだまだ少ない。だからこそ、能作の製品には大きなチャンスがある。文化の違いを理解し、それに合わせた提案をすることが、グローバル市場での成功につながる。
一方、MAEは「人と社会に新陳代謝を」という理念のもと、医薬品の分野で培った技術を別の分野に応用しながら、新しい価値を生み出している。
「医薬品業界での経験やノウハウを、異なる業界や海外市場に活かせたら、もっと可能性を広げていけると考えています」と石川は言う。
こうした挑戦を続ける両社の姿勢は、これからの地方創生の新しいモデルとなるかもしれない。
「マーケティングや各国の文化をリサーチしながら、富山のものづくりの魅力をどう伝えていくかを考え続けることが大事だと思っています。」
千春さんのこの言葉は、「人と社会に新陳代謝を」というMAEの理念とも響き合う。
富山の自然や文化を活かしながら、世界の多様な価値観を理解し、それぞれの市場に合った提案をしていく。
ローカルからグローバルへ——この視点こそが、富山のものづくりを未来へつなぐ鍵となる。
-
能作克治
株式会社能作 代表取締役会長
1958年福井県出身。大阪芸術大学芸術学部写真学科を卒業後、新聞社勤務を経て、1984年に義父が経営する能作に入社。2001年東京原宿バージョン ギャラリー展示を機に、直販を徐々に拡大。2002年に代表取締役社長就任。国内に19店舗、台湾に2店舗の直営店を展開しているほか、アジアや欧米など海外にも積極的に展開。2013年「第5回ものづくり日本大賞 経済産業大臣賞」を受賞。2016年、藍綬褒章を受章。ダイヤモンド経営者倶楽部 2022年度「マネジメント・オブ・ザ・イヤー」大賞受賞。
能作千春
株式会社能作 代表取締役社長
富山県高岡市出身。神戸学院大学を卒業後、2008年に神戸市内のアパレル関連会社で通販誌の編集に携わる。2011年に株式会社能作に入社し、現場の知識を身につけるとともに受注業務にあたる。製造部物流課長などを経て、新社屋移転に向け産業観光部長として新規事業を立ち上げる。2018年に専務取締役に就任。2023年、代表取締役社長に就任。Forbes JAPAN「WOMEN AWARD 2023」入賞。2024年に錫ジュエリーブランド「NS by NOUSAKU」をローンチ。

福島県出身。大学院卒業後、薬剤師として外資系製薬企業に勤務。医薬品の品質・製造管理の業務に携わる。2021年に前田薬品工業株式会社へ入社。医薬品業務の傍ら「新蒸留研究所」を立ち上げる。製薬の研究開発・製造ノウハウを、香りの研究や蒸留酒の開発製造領域へ展開することに取り組む。
