まえに、いるひと MAE PEOPLE

まえに、いるひと MAE PEOPLE
MAEとコクヨがつくる、新しい学びとつながりのかたち

-
「ヘルジアンウッド」や「新蒸留研究所」、サウナホテル「The Hive」、歴史ある建物を活かした「土肥邸母屋」など、次々と新しい挑戦を仕掛けているMAE。
そして新たに取り組んでいるのが、富山の廃校を活用するプロジェクト。ここでタッグを組んだのが、「be Unique.」を企業理念に掲げ、「働く、学ぶ、暮らす」のあり方を提案し続ける「コクヨ」だ。
一見、異なる領域で活躍する両社。でも、その根底にあるのは「枠を超えて新しい価値を生み出したい」という共通の思い。廃校という場を活かしながら、どんな化学反応が生まれているのか?そして、このプロジェクトを進めてきたMAEの大久保と、コクヨの川田さんが見据える未来とは?——2人の言葉を通して、この挑戦の本質に迫る。




-
偶然の出会いから、未来の学び場へ
「薬のない世界を作る」
そんなユニークなビジョンを掲げるMAE。健康を軸にしながらも、製薬の枠にとどまらず、様々なプロジェクトに挑戦してきた。
そして今、MAEが新たに手を組んでいるのは、文房具やオフィス家具で知られる「コクヨ株式会社」だ。でも、一体どうしてこの2社が?そのはじまりは、意外なことに「サウナ」だったという。
MAEの執行役員・大久保も、こう振り返る。「サウナがなかったら、多分コクヨさんとの今の関係は生まれていなかったと思います。」
コクヨは文房具だけでなく、「働く、学ぶ、暮らす」といった事業領域の拡張にも力を入れている。特にコロナ前後から、ワークスタイルの変化に対応するため、地方でのワーケーションの可能性を模索していた。
その視察先の一つが、富山だった。実は、コクヨの創業者 黒田善太郎氏のルーツは富山にあり、富山大学には「黒田講堂」という建物が今も残っている。
「学びを提供する会社として、この講堂が今も学生の方に現役で利用いただいていることに驚きました。これを、もっと多くの人に伝えたいと思ったんです」と語るのは、コクヨの川田さん。
視察中、県庁がコクヨチームに紹介した訪問先のひとつが「ヘルジアンウッド」だった。そこで川田さんは、MAEの社長である前田と初めて出会うことになる。
「ヘルジアンウッドへ向かう車中で前田さんの写真を見たんですが、『この人、絶対サウナ好きだわ』ってぼんやりと感じていました(笑)」実際に会ってみると、やはりサウナが好きだった。川田さんは普段から、サウナが好きそうな人にはコクヨの名刺と、自身のサウナ関連の名刺をセットで渡す習慣があるとのこと。その日も2枚の名刺を渡すと、「あのサウナプロデューサーのカワちゃん?」と前田に言われ、そこから一気に話が弾んだ。
一緒にヘルジアンウッドを巡る中で、前田が熱く語ったのが「サウナホテル構想」だった。
「前田さんが『ちょうどよかった、あそこを見て!』と、想定の5倍くらいの熱量でバァーと語ったんです。『あそこのハーブ園の向こう側にサウナホテルをつくろうと思っているんだよ』と。それが、後の『The Hive』のきっかけでした。」
川田さんは、富山で出会ったMAEの取り組みに感銘を受け、東京へ戻るとすぐに社内に報告し、両社トップの正式な顔合わせが実現する。
MAEとコクヨは互いのビジョンに共鳴したが、何か取り組みを一緒に出来れば…という程度にその時は留まった。一方で、サウナホテル「The Hive」のプロジェクトを進める中、サウナ体験の構築に精通している川田さんに協力を依頼。Ushareの上田さんやプロジェクトメンバーの力のおかげもあり、2年がかりでついにサウナホテルが完成した。原風景の中で大地に包み込まれるような設計は、自然との一体感を追求した前田のこだわりが詰まっている。
サウナホテルが形になっていく中で、川田さんの富山への関心はさらに深まる。そんな時、前田から廃校となった立山町立日中上野小学校の話を聞いた。当時はまだ構想段階だったが、「卒業生や県外・海外から訪れる人々が交わる、新しい学びの場をつくれたらいいね」と。そのアイデアは、サウナホテルのプロジェクトを進めながらも、ずっと話題に上がっていたという。
一方で、大久保は「廃校の活用は、立山町全体の課題だった」と振り返る。
「町にはすでに廃校となった小学校がいくつもあって、どう活用していくかが大きなテーマになっていました。地域外の企業が入るケースもありますが、できるだけこの地に関係した人たちの手で、地域の未来をつくってもらいたいという地元の思いがあったんです。」
もともとはMAEのみで、廃校を活用する道を模索していた。しかし、もっと大きなインパクトを生み出すには、同じ思いを持つ仲間が必要だと考えた。そんな中、黒田社長との顔合わせの時の想いとサウナを通じて信頼関係を築いていた川田さんの顔が一番に浮かび、コクヨに相談することにした。
「お話を伺った時、MAEが地方の教育課題に対して新しいアプローチを考えていることがすごく伝わってきました。だからこそ、『それ、ぜひコクヨでやらせてください!』と即答しましたね。」
サウナホテル「The Hive」のプロジェクトを通じて培った信頼が、新たな挑戦へとつながっていく。業界の枠を超えたコラボレーションが、地域の未来を動かそうとしている。

-
協業が生み出す新陳代謝
「廃校を再生し、新しい学びの場をつくる」
MAEとコクヨが進めるこのプロジェクトは、ただのリノベーションではない。両社の知見や文化が混ざり合いながら、進化し続ける取り組みだ。まさに新陳代謝のように、常に進化しながら形をつくっていく。
でも、こうしたプロジェクトを続けるには、ちゃんと経済的に成り立つ仕組みも必要だ。大久保は、その重要性をこう語る。
「民間企業で教育事業を続けていくためには、お金がきちんと循環する仕組みが欠かせません。でも、もしこのプロジェクトが一つの成功例になれば、全国にある廃校が新しい価値を生み出す場になっていくかもしれません。」
ただ一度のプロジェクトで終わらせるのではなく、持続的に価値を生み出すモデルになれば、日本各地の地域課題にも新しい光が差し込むかもしれない。
このプロジェクトの出発点には、ある思いがあった。
「この廃校を利活用すれば、新しい教育のあり方、教育を再定義できる場を作れるのではないか——」
という思いだ。大久保は、進める中で改めて教育の本質を考えさせられたという。
「教育って、正解がないんですよね。学ぶことも、アウトプットすることも、時代や環境によって変わっていく。だからこそ、人もこの場もどんどんアップデートしていかなきゃいけないと思いました。」
学校という枠を超え、学びの形そのものを問い直していく場。このプロジェクトは、そんな場所を目指している。



- 一緒に走る、頼れるパートナー
-
限界集落と呼ばれる地域では、若い世代が定着する環境が整っていない。特に、学校がなくなると、子どもを持つ家庭は他の地域へ移り住み、結果としてさらに人口が減っていく。
この負のループを断ち切るために、MAEとコクヨは廃校を再生し、新しい学びの場をつくることにした。そこには、長期的なパートナーシップが欠かせない。そんな中で、MAEにとって、コクヨは理想的なパートナーだという。「コクヨさんの仕事の進め方が素晴らしいんです。スピード感があるのはもちろんですが、それ以上に、ずっと伴奏してくれている感じがあるんですよね。」
一つのプロジェクトとして進めるのではなく、「なぜこれをやるのか?」をしっかり理解しながら、一緒に考え、動いてくれる。そんなスタンスが、MAEにとって大きな支えになっている。
大久保自身も、新しい挑戦を続けてきた。薬学部を卒業後、27歳で富山に移り、MAE(当時は前田薬品工業)に入社。当初は品質部門にいたが、次々と立ち上がる新規事業に関わるうちに、「やってみたい」という気持ちがどんどん強くなっていった。
「毎年新しいプロジェクトが立ち上がるので、そのたびに『やらせてください!』って手を挙げていましたね。」
この姿勢は、MAEの文化そのものである。「新しいことに挑戦し続けることは、企業としても、個人としてもすごく大事。成功するかはやってみないと分かりませんが、挑戦し続けることで成長につながると思っています。」
コクヨにとっても、この協業は大きな意味を持っていた。
「地域にどう貢献できるのか。もっと効果的な方法があるんじゃないかと、ずっと模索していました。そんな時、現在では年間400校もの小学校が廃校になっていると知ったんです。」
「デスクや椅子、収納など、小学校と長く関わってきたコクヨだからこそ、何かできることがあるんじゃないか——」
そんな思いが、MAEとの協業につながっていった。
このプロジェクトの特徴の一つは、コクヨ内でDAO型組織*として運営されていることだ。通常なら、特定の事業部が担当するところを、「やりたい!」と手を挙げた社員たちが集まり、チームを形成している。
川田さんをはじめ、地方とつながる部門が窓口として伴走しながら富山にオフィスを構えるコクヨグループの「コクヨ北陸新潟販売」、そして、インハウスデザイナーに元コクヨの設計部門(現株式会社WATARU ARCHITECTS)など、企画から設計・構築まで、多様な機能と人材が想いを持って参画している。さらに、コクヨでは社内複業制度「20%チャレンジ」の制度を活かし、学びの領域としてステーショナリー部門のメンバーや学生時代に教育領域に携わっていた専門家なども加わり、持続的な組織でプロジェクト化している。
「自主的に関わるメンバーが集まることで、より深い理解とコミットメントが生まれています。」
こうしたフラットな組織体制が、新しいアイデアを生み出す原動力になっている。
*特定の所有者や管理者が存在せずとも、メンバーが自律的に意思決定し、事業やプロジェクトを推進できる組織のこと



- MAEのカルチャーが生み出す、新しい流れ
-
コクヨの川田さんが感じたMAEの魅力は、そのビジョンの大胆さにあるという。
「製薬会社なのに『薬のない世界をつくる』って、すごく面白いですよね。一見、矛盾しているように見えるけれど、健康という本質はしっかりと見据えている。そこが、MAEのあらゆる取り組みに生きているんだと思います。」
もう一つ印象的なのは、「地域との向き合い方」だ。
「普通は、ビジネスとしてマーケットを考えるものだけど、MAEはむしろ富山に村をつくろうとしている。そのスケールの大きさに、正直びっくりしましたね。」
そして、コクヨがMAEに共感したもう一つの理由が、「新陳代謝」という考え方だ。
「新陳代謝って、古いものを新しく生まれ変わらせることですよね。コクヨでも『伝統と革新』を大事にしているので、どうやって既存の価値を新しい形に変えていくかは、常に考えています。」
これは、企業だけでなく、個人にも当てはまる話だ。
「企業のあり方も、働く人の意識も、自分たち次第で変わっていく。そういうプロセスこそが新陳代謝だと思うし、MAEにぴったりな言葉だなと感じました。」
MAEとコクヨの協業は、単なる企業同士の連携ではなく、組織や個人が新しい挑戦を重ねることで生まれる新陳代謝の象徴のようなものなのかもしれない。
このプロジェクトの背景には、人と人との関係性がある。川田さんは、MAEの組織文化を支える前田と大久保の関係に注目していた。
「どこへ行っても『前田さん、前田さん』って名前が聞こえてくるんですよ。最初は、前田さんが5人くらいいるんじゃないかと思うくらいでした(笑)。どうやってこんなに幅広く動いているのか、不思議でしたね。」
その答えが、今回の対談相手である大久保だった。
「実は大久保さんの名前も、あちこちで聞いていたんです。だから最初は『大久保さんも5人くらいいるのかも?』と思ってました(笑)。でも実際に会ってみると、大久保さんが膨大な業務をこなしながら、プロジェクトを支えている姿に驚きました。」
どんなに革新的なビジョンを持つリーダーがいても、その人だけでは物事は動かない。
「大事なのは、それを形にし、継続的に動かしていくパートナーの存在。そういう人がいることで、プロジェクトはさらに広がっていく。大久保さんの包容力や調整力は、まさにその役割を果たしていると感じました。」
こうした人と人との信頼関係が、新しい教育の形を生み出し、地域の未来を切り拓いていく。そして今回の廃校プロジェクトでも、大久保と川田さん、それぞれの実行力が、MAEとコクヨの協業を成功へと導いている。

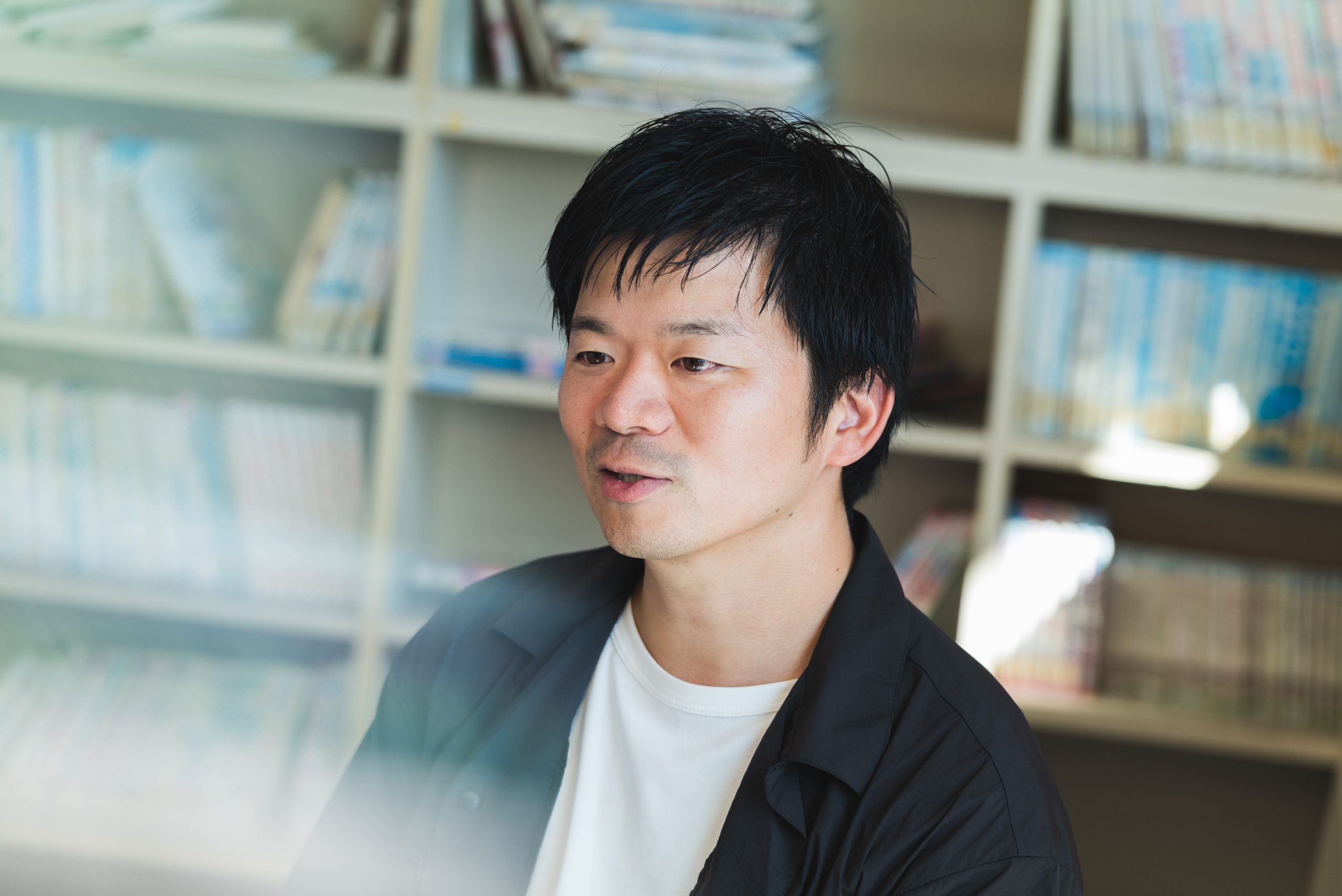

-
未来へつながる学びの場
廃校になった小学校を舞台に、MAEとコクヨが描くのは、ただのリノベーションではない。教育をもう一度見つめ直し、地域に新しい風を吹き込むこと。そんな大きなビジョンをもとに、プロジェクトは動き続けている。
「この場所は、関わる人によって価値が変わっていく。大事なのは、私たちの世代だけで完結させないこと。次の世代がまた新しい価値を生み出していくような、そんな場になればいいなと思っています。」
だからこそ、この場をひとつの完成形にするのではなく、コクヨをはじめ、さまざまな企業や人たちと一緒に、新しいプロジェクトを生み出し続けていく。それこそが、この場所の面白さなのかもしれない。
この取り組みを、川田さんは「楽園小学校」という言葉で表現する。
「小学校って、誰もが一度は通ったことや関わりのある場所ではないでしょうか。でも、これからの時代、『卒業のない小学校』があってもいいんじゃないかと思うんです。」
ここに関わる人は、年齢も職業もさまざま。3歳の子どももいれば、企業の役員や政治家、アーティストもいる。そんな人たちが立場を超えて学び合い、関係が広がっていく。そんな場所になったら、きっと面白い。
この「楽園小学校」は、決まったプログラムのある学校ではなく、常に変化し続ける実験の場だ。
「数年前はこんなことをしていたんだ」
「来年は自分も関わりたいな」
そんなふうに、関わる人が自由に行き来しながら、学びと交流の場を広げていく。
このプロジェクトには、あえて「すべてを決めすぎない」というスタンスがある。川田さんは、その理由をこう語る。
「すべてを決めてしまわず、余白を残しておくことも大切なんです。時代に合わせて変わっていけるように、新しい仲間とともに考え、変化を楽しみながら進めていきたいと思っています。」
確かに、きっちり計画されたものよりも、関わる人が自由に動ける場のほうが、想像もしなかったアイデアが生まれる。そんな柔軟な姿勢こそが、このプロジェクトの本質なのかもしれない。
この場所に関わるメンバーは、互いに刺激を受けながら、新しいアイデアを生み出している。川田さんも、この循環の面白さを感じている。
「まさに新陳代謝が起きています。ここから生まれたものが、また次のプロジェクトにつながっていく。それが、この取り組みの醍醐味なんです。」
MAEとコクヨの挑戦は、廃校の再生にとどまらない。教育のあり方を問い直し、地域の未来をつくり、人と社会の新しい流れを生み出していく。これは、ただのプロジェクトではなく、まだ誰も見たことのない未来の実験だ。
そして、その実験は、これからも進化し続ける。
-
川田直樹
コクヨ株式会社、一級建築士、サウナ部長
奈良県生まれ大阪育ち。オフィス空間の設計・工事を手掛けるコクヨのグループ会社に入社し、現在で勤続20年。コクヨ株式会社の社長室 兼 新規事業の部署を歴任し、現在はオフィス構築関連部門において組織人材の開発領域に従事。また、本業の傍ら、コクヨグループ内で総勢180名のサウナ部の立ち上げをきっかけに、他社のサウナ部も巻き込んだ団体「JAPAN SAUNA-BU ALLIANCE」を設立、共同代表を務める(加盟企業240社5000名)。さらに、独自のサウナへの利用者目線と設計者目線を併せ持つ強みを活かし、既存施設のリブランディングや新規構築からサウナ飯の開発までサウナプロデューサーとしても活躍中。

長野県出身。大学院を卒業後、薬剤師として前田薬品工業株式会社に入社。品質保証部門、商品開発部門を経て2017年より新規事業に従事。現在は、人と地域の未来を考え、美しさと健康の実現のために新規事業や天然富山県産アロマブランド「Taroma(タロマ)」の商品開発にも取り組んでいる。
